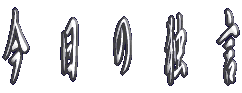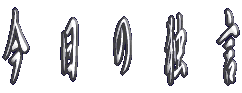|
この鑑定所での理想モデルは「鬼市(中国)」・「silent trade(英)」です。
鬼市というのは − 現代でもどこかの奥地で行われている可能性があるけれど − かつて異民族間での取引にしばしば用いられていた方式です。
売り手が商品を運んできて所定の場所、恐らく何百年もの間、先祖代々決められていたところにそれを並べ、一度姿を消します。
すると買い手の側が姿を現し、気に入った商品のわきに相当と思われる銀とか物品(物々交換の場合)を置いて立ち去ります。
翌日、またはどこか物陰で買い手が去るのを見届けた売り手が出てきて金額(代りの品)を検討し、納得がいけばそれを持ち帰り、売り手がいなくなった後で買い手が商品を自分のものとするわけです。
売り手は値が気に入らなければ再び姿を消し、相手が増額するのを待ちます。
より高い値段を付けても入手する価値があると買い手が考えているときはさらに上乗せしますが、これ以上出せないというのであれば、先に出した銀等を撤収します。
売り手は商談を継続する意志がある限り、商品をその場に残しておき、最早これまでと打ち切りを決定すると持ち帰ってしまいます。
このようにして互いの信頼関係だけにより成り立っていて、余計なトラブルの元となるコミュニケーションを回避する商取引が「鬼市(silent trade)」なのです。
私には、これこそ取引における一つの理想的な形だと思えるのです。
数百年、或いは千年以上黙々と続けられていた取引 − 「自分と違う人との相互理解と友好」という発想とは別な方向に発達し、洗練された、ヒトとしての本能に直接根ざした美しい形式!
なお、かつてのサバでの乳香取引などでは、売り手が希望額を書いた札を商品に添えておいたり、取引の場を兵士が警護している、と「鬼市」と呼ぶにはかなり手が加えられ複雑化していたようです。
(参考: 山田憲太郎・著、『香談 東と西』法政大学出版局)
|